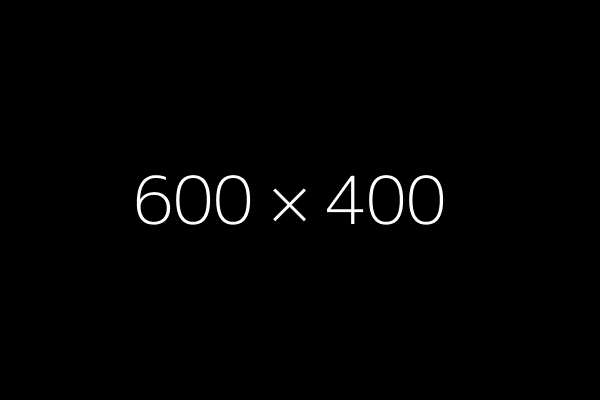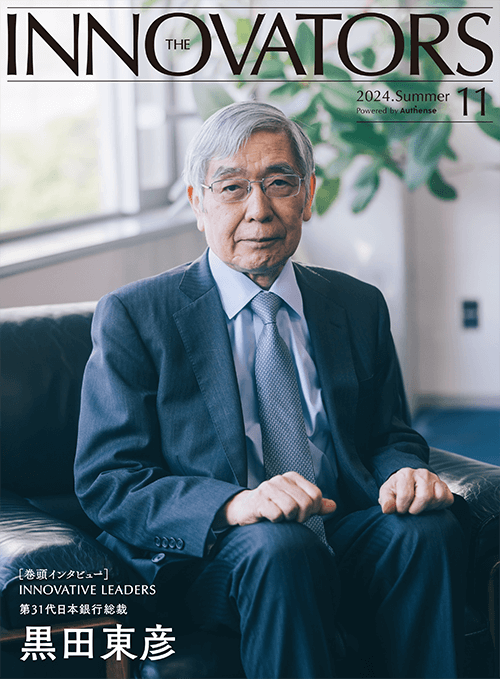いつも「Legal Tips」をお読みいただきありがとうございます。
今回のテーマは、「事業承継」と「遺留分」です。
「事業承継」は、会社を経営されている経営者の方にとっては、避けては通れない大問題の一つです。
ただ、事業承継と一口にいっても、経営者の方が考えるべきことは多岐にわたります。誰を後継者にするのか、いつ事業を後継者に引き継がせるのか、お金(税金)の問題はないのかなどなど、一人では明確な答えが出せないことも多いと思いのではないでしょうか。
今回は、事業承継を、「自社株や事業用資産の後継者への承継」という視点から考えてみたいと思います。
経営者が保有する財産を、後継者に引き継がせる方法として、売買、贈与や相続など様々な方法が考えられます。そして、贈与や相続などで財産を承継する場合には、後程説明するとおり、「遺留分」に関する問題を考えなければなりません。
それでは、自社株や事業用資産(以下「自社株等」といいます。)の承継と遺留分に関する問題及びその対策方法についてみていきましょう。(今回のメインのお話は4項からですので、お時間がない方はそちらからお読みください。)
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
1 財産の承継という観点
まず、自社株等の承継がなぜ遺留分と関係があるのか疑問に思われる方もいらっしゃると思います。以下、簡単に説明いたします。
自社株等(主に非上場株式)は、漠然と会社の財産と考えがちではないでしょうか。そのため、後継者に対して会社を引き継ぐ以上は、自社株等は当然に引き継がれると、漠然と考えていらっしゃる方もおられるかもしれません。
しかし、自社株等は、経営権である以上、経営者個人の財産として保有している場合がほとんどではないでしょうか。この場合、自社株等は経営者個人の財産であり、会社のものではありません。
また、個人の財産であるということは、当然に、相続の問題があります。経営者の方が亡くなり、相続が発生した場合には、自社株等は相続される財産の一つです。すなわち、経営者個人が保有する自社株等は、遺産として、相続人が相続することになるのです。
もし、会社の後継者が相続人以外であった場合、何らかの対策を取っていなければ、後継者の方は自社株等を相続により取得することはできません。
ここまでの話でお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、経営者個人が保有する自社株等は、個人の財産として考えた場合、預金や不動産などの財産と同様に考えることができます。
そして、財産を贈与や遺贈するにあたっては、遺留分という問題を考えると思います。
そうすると、自社株等を贈与や遺贈によって承継させる場合も、「遺留分」という問題を考えるべきとお気づきになることでしょう。
このように、経営者の方が保有する自社株等を、贈与や相続によって後継者の方に承継する場合には、遺留分のことを意識し、必要に応じて対策しなければならないということになります。
2 遺留分について
まず、本題に入る前に、「遺留分」について、基礎的な事項をご説明いたします。
(1)遺留分は、被相続人の財産の中で、法律上その取得が「一定の相続人」に留保されていて、被相続人による自由な処分に制限がある持分的割合のこと、などと説明されます。法律上は、民法1042条以下に規定があります。
そして、贈与や遺贈によって、他の相続人が多く財産を受け取ってしまい、その結果として遺留分に満たない財産しか受け取れなかった相続人(遺留分を侵害されている相続人)は、他の相続人に対して、遺留分に足りない部分について請求を行うことができます。これを、遺留分侵害額請求といいます。
(2)なお、遺留分は、全ての相続人に保障されているわけではありません。
相続人のうち、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分は保障されていないので、注意が必要です(民法1042条参照)。
(3)遺留分侵害の有無及び侵害されている金額については、以下のように計算されます。
- ①遺留分算定の基礎となる財産額の確定
被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、贈与された財産を加えたものから、相続債務の残額を引いた金額がこれにあたります。 - ②各相続人の個別的な遺留分の割合の確定
2分の1(相続人が直系尊属のみの場合3分の1)×各人の法定相続分 - ③各相続人の個別的な遺留分の金額
①×② - ④各相続人の遺留分侵害の金額
③-当該相続人が相続によって得た財産額―特別受益額+相続債務分担額
(4)なお、上記(3)①の中の「贈与された財産」については、以下のように判断がなされます。
被相続人の生前に行われた贈与については、相続人に対する贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与を除き、相続開始前の10年間になされたものが遺留分を算定するための財産の価額に加えられます。また、相続人以外の者に対する贈与の場合、相続開始前の一年間になされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に加えます。
(5)そして、上記(3)④の計算の結果、遺留分が侵害されていた場合、遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた者や遺贈を受けた者に対して、遺留分を侵害された金額に相当する金銭の請求を行うことができることになります(民法1046条)。
では、具体的な事案で、遺留分侵害額請求について確認してみましょう。
被相続人Aが死亡し、その相続人は、妻Bと、子C及びDとします。相続開始時の遺産は、不動産1000万円、預貯金2000万円とします。そして、被相続人が亡くなる5年前に、被相続人から、子Cに対して金9000万円の贈与がなされました。遺産分割協議では、妻が不動産と預貯金1000万円を、子Dが残りの預貯金1000万円を取得することになりました。
- 遺留分算定の基礎となる財産額
1000万円+2000万円+9000万円=1億2000万円 - 各相続人の個別的な遺留分の割合の確定
妻B2分の1×2分の1=4分の1
子C2分の1×4分の1=8分の1
子D2分の1×4分の1=8分の1 - 各相続人の個別的な遺留分の金額
妻B1億2000万円×4分の1=3000万円
子C1億2000万円×8分の1=1500万円
子D1億2000万円×8分の1=1500万円 - 各相続人の遺留分侵害の金額
妻B3000万円―2000万円=1000万円
子D1500万円―1000万円=500万円
以上のとおり、妻Bと子Dは遺留分が侵害されていますので、それぞれ子Cに対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
-
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
-
メールでご相談予約
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
3 自社株等の承継を行った場合
では、上記(6)の事案を、被相続人Aが会社の経営者、子Cが会社の後継者とおきかえて考えてみましょう。
経営者であるAは、後継者のCに会社を継いでもらうべく、亡くなる5年前に、Aが保有する会社の自社株等を、後継者であるCに対して全て贈与しました。自社株等の贈与時の価格は、1000万円でした。Cは、2代目の経営者として経営努力を重ね、会社を大きく成長させました。その結果、Aが亡くなった時点では、Cが承継した自社株等の評価額は9000万円にまで上昇していました。
もし、Aが何らかの対策をしていなかった場合には、BとDが、Cに対して遺留分侵害額請求をした場合、CはBとDに対して、それぞれ金銭を支払わなければならないことになります。
もし万が一、Cが金銭を準備できなければ、裁判所に対して、支払いについて相当の期限を許与してもらうよう請求することはできますが、支払いを免れることはできません。Cに手持ちがなく、支払いが難しいような場合には、自社株の一部を手放したり、事業用資産を売却して金銭に変えたりして、金銭を支払う可能性もあり、このような事態が生じることは、事業承継にとって大きなマイナス要因となり得ます。
4 事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例
(1)では、事業を承継するにあたり、遺留分の問題に対して、何らかの対策をすることはできないのでしょうか。
もちろん対策方法はあります。
いくつか方法がありますが、今回は、この項のタイトルでもある、「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の活用をご紹介したいと思います。
(2)この遺留分に関する特例については、「除外合意」(法4条1項1号、5条)と「固定合意」(法4条1項2号)がポイントとなります。
株式等を承継するにあたり、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員の合意の上で、現経営者から後継者に贈与等された自社株等について、
①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)又は、
②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)
をすることができます(両方を併用することも可能です。なお、固定合意ができるのは、会社の自社株のみになります)。
以下、詳しく説明いたします。
(3)まず、①の除外合意です。
これは、上記2の(3)の①で説明した計算を行う場合の特例といえます。
すなわち、後継者を含めた推定相続人全員が合意をすれば、自社株等の贈与については、遺留分算定の基礎財産に算入しないことができるのです。
分かりやすく考えると、上記2の(6)の①の計算の中で、(+9000万円)の部分がなくなることとなります。
つまり、この除外合意が成立すれば、後継者は、自社株等を被相続人から承継したことを理由としては、遺留分侵害額請求をされることがなくなります。
したがって、除外合意を成立させることができれば、円滑に自社株等を後継者に承継することが可能となります。
(4)次に、②の固定合意です。
これは、上記2の(3)の①で説明した計算を行うにあたり、除外合意とは違い、自社株の贈与についても遺留分算定の基礎に算入はします。
しかし、その金額を、合意した時点の金額に固定するというものです。
何故このような合意を行うことに意味があるかといいますと、遺留分算定の基礎となる贈与の評価額は、贈与時点の評価額を基準としません。相続開始時点での評価額を基準とするのです。
そうすると、上記3の事例のように、後継者が自社株を相続した後に、努力して会社を成長させ、自社株の価値を上げれば上げるほど、他の相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクが高まっていく、という不都合が生じるのです。
このようなリスクを未然に防ぐため、固定合意をしておくことで、後継者が自社株の評価が上昇したことを理由として遺留分侵害額請求を防ぐことができるのです。
したがって、固定合意をすることでも、円滑に自社株を後継者に承継することが可能となるのです。
(5)上記の特例を利用するためには、会社であれば中小企業であることや、経済産業大臣の確認を得ることなど、様々な要件があります。
分かりやすい説明が中小企業庁のホームページでなされておりますので、是非一度中小企業庁のホームページもご参照ください。
なお、Authense法律事務所では、多様な企業法務ニーズに対応するさまざまな料金プランをご用意しております。ぜひ一度ご覧ください。
また、即戦力の法務担当者をお探しの企業様に向けた「ALS(法務機能アウトソーシングサービス)」のご案内など、各種資料のダウンロードも可能ですので、こちらもぜひご確認ください。
5 終わりに
今回は、「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」について紹介いたしました。事業承継は、会社にとって非常に重要な手続きです。ですが、一筋縄でいかないことも多いです。弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めることを強くお勧めいたします。弊所にもお気軽にご相談ください!