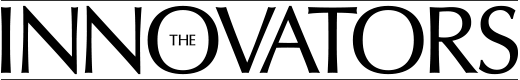毎年12月、清水寺の舞台で大筆をふるってその年を象徴する漢字一文字を書く「今年の漢字」は多くの方が目にしたことがあるはずだ。
1995年から始まった本イベントでは、森清範師は一発勝負で毎年書き上げている。
清水寺で「今年の漢字」を書く意味や意義について話を聞いた。
取材/元榮太一郎(本誌発行人) Taichiro Motoe・山口和史(本誌編集長) Kazushi Yamaguchi
文/山口和史 Kazushi Yamaguchi 写真/西田周平 Shuhei Nishida
「今年の漢字」が清水寺にもたらしたもの
- 森貫主は、「今年の漢字」を清水寺奥の院の舞台で揮毫していることでも広く知られている。「今年の漢字」は、公益財団法人日本漢字能力検定協会が主催している。日本全国から応募された「今年の世相を表す漢字一字とその理由」を集計し、最多数の漢字を森貫主がぶっつけ本番で大筆を揮って書き上げている。
森師: 清水寺で発表したいと依頼があったんです。今年で30年になるんですけどね。1995年(平成7年)、阪神・淡路大震災の年から始めたんです。これは日本漢字能力検定協会が漢字普及のために何かできないかという趣旨で考えついた行事です。依頼を受けて、周囲に相談したところ、『やらはったらどうですか』とご賛同いただいたので始めたんです。
いまでは、私が頼まれて講話に行くと、全国の皆さんが知っておりますね。私のことは知らなくても『今年の漢字』は知っているんですよ(笑)。
- 「今年の漢字」は、先述したように森貫主が勝手に決めているわけではない。毎年、発表当日の朝、漢検の理事長が二重封筒になって外から判読はできない状態にした一字を森貫主とともに開封し、発表の段取りとなる。森貫主は練習なしに、一発勝負で毎年揮毫している。
森師: 全国の人から募集して決めている字なんですけれども、なかには私が決めていると思っている人もいらっしゃるんです(笑)。
あの発表の行事、私は意味があると思うんです。私が今年の漢字を考えるのではなく、たくさんの方が『この字だろう』と、それぞれその年の思いを込めて漢字を決めている、これがいいと思うんです。
- 森貫主は日本全国、さまざまな場所で講演や講話を行っている。その時、依頼を受け漢字一字を揮毫する機会が多くある。修学旅行で訪れる小中学生にも「一字」をプレゼントする場面が増えたという。
森師: 清水寺のパンフレットに漢字を書いて贈るんです。すると、その字とその子がピタッと合うんですよ。彼らが自分で合わせるんですね。『学』という字を書いた子は『自分は一生懸命勉強しなきゃいけないんやという思いを持ちました』とかね。
この前、大谷翔平さんの『翔』という字を書いてあげたんですよ。そうしたら感想文で、『僕は学校で大谷翔平に顔がよく似てると言われている』と。『良い字をもらった、僕も一生懸命、翔平さんのように努力をしてがんばります』と送ってきたりね。そうやっていいように思ってくれるんですね。
「三方良し」の考え方をビジネスにどう活かすか

- 世俗を離れ、仏門で修行を続ける森貫主。日々、激変するビジネスの世界で生き馬の目を抜く日々を暮らすビジネスマンに、仏教の世界からアドバイスを贈るとしたらどのような言葉になるのだろうか。
森師: やはり高望みをしないということですね。あまり高望みをすると、そこに至らないときにストレスになるんですね。希望を持つことは素晴らしいことですが、その望みに執着をしないということでしょうね。また、オレがオレがと主張しすぎると、人間関係がうまくいかないと思うんです。だから相手を思いつつ、自分は努力することが大切じゃないかと思いますね。
近江商人の『三方良し』という言葉がありますね。売り手良し、買い手良し、世間良しと。世間というのが、この考え方の素晴らしい点だと思います。この言葉も仏教の思想から来ているんですよ。
売り手良しと買い手良しと、二人が揃って、そして心が一致したときに手打ちをしますね。それでいきましょう、ポンってね。あなたと私とがひとつになる。気持ちが一体になる、この考え方は私が『観』で相手が『音』なんですよ。向こうからすれば向こうが『観』で私が『音』です。観と音がひとつになったときに観音なんです。このひとつになったときに大慈悲心という相手を思いやる境地になるんですね。それがすなわち世間が良しに繋がるのです。第三者の世間のためにもなり、みんなが喜んでいると。その第三者というのは先祖であり、神であり仏であると。そういった存在ですね。宗教的に言えば、この三者がみんな喜ぶことが素晴らしいことではないかと、そう思うんです。
これは商売に限ったお話しではありません。現在の政治の世界も、世界情勢についても同様なんです。あなたの国と私の国が仲良くなった、それだけではダメなんです。周囲の国も『そうだな』『なるほど』と。これで初めて友好関係が成り立つんです。ふたつの国だけが得をする考えではダメなんです。
だから、三方良しの考え方というのは、ビジネスにも合うし、世界平和にも合うし、人間関係にも成り立つ教えなんですね。非常に良い教えを先祖は残しているなと。こういうふうに思うんですね。
- 2025年で85歳となる森清範貫主。1200年以上の伝統と歴史を守りつつ、より広く、より深く仏教の教えを伝えるため、今後も活動を続けていく。
Profile
森 清範 師
1940年、京都・清水生まれ。1955年に当時の清水寺貫主、 大西良慶の元に弟子入り。1963年、花園大学卒業。真福寺住職を経て1988年に清水寺貫主、北法相宗管長に就任。1995年からは財団法人日本漢字能力検定協会が主催する「今年の漢字」を、清水寺の舞台上で揮毫している。「清水寺まんだら」(春秋社)、「心を摑む」(講談社)、「四季のこころ」(KADOKAWA)など著書多数。