企業としては、せっかく雇用した従業員にはできるだけ退職してほしくないと考えることでしょう。
また、従業員に突然退職される事態は、避けたいことだと思います。
では、就業規則で従業員の退職を制限したり、退職3か月前までに申し出るべきなどの規定を設けたりすることはできるのでしょうか?
今回は、就業規則で退職を禁じたり制限したりすることの可否や、退職に関して労使間で発生しがちなトラブルについて、社労士がくわしく解説します。
退職の種類
一口に「退職」といっても、退職にはさまざまな種類が存在します。
はじめに、退職の種類を紹介します。
自然退職
自然退職とは、会社や従業員が意思を表示することなく、自動的に労働契約が終了する形での退職です。
自然退職は、就業規則や雇用契約書に定めた要件を満たした場合に発生します。
そのため、自然退職を発生させるには、就業規則や雇用契約書による定めがなければなりません。
就業規則で定める自然退職の事由としては、次のものなどが考えられます。
- 従業員の死亡
- 従業員が一定の年齢に達したこと(定年)
- 一定期間の無断欠勤
- 一定の休職期間を満了しても復職ができないこと
ただし、自然退職となる事由について、会社が自由に定められるわけではありません。
たとえば、「妊娠したこと」や「婚姻したこと」などを自然退職の事由として規定することは、男女雇用機会均等法の「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」との規定に違反しています(男女雇用機会均等法9条)。
このように、自然退職事由の定めは、内容によって違法となる可能性があるため注意が必要です。
自然退職に関する規定についてお困りの際は、社労士へご相談ください。
合意退職
合意退職とは、会社と従業員との合意により雇用契約を解除することです。
合意退職には、次の2つのパターンがあります。
- 従業員側から退職を申し出て、会社が受理するパターン
- 会社側から退職を申し入れて、従業員が承諾するパターン
いずれであっても、両者が合意する限り円満な退職となります。
なお、このうち「2」にあたって会社側から退職を申し入れることを、「退職勧奨」といいます。
退職勧奨は解雇とは異なり、従業員がこれに応じるかどうか自由でなければなりません。
従業員に対して心理的圧力を加えるなど、事実上退職勧奨に応じるしか選択肢がなかった場合は解雇であると判断され、後にその適法性が争われるおそれがあります。
後のトラブルを避けるため、退職勧奨をしようとする際は、あらかじめ社労士や弁護士へご相談ください。
辞職
辞職とは、従業員の一方的な意思表示による退職です。
従業員が退職を申し入れた際、会社がこれに合意すれば「合意退職」、会社が合意しない場合は「辞職」となります。
民法では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定されています(民法627条1項)。
この規定により、期間の定めなく雇用されている従業員は、会社に対していつでも退職を申し入れることができます。
また、申入れから2週間が経過することで、自動的に退職となります。
つまり、従業員が退職を申し入れた際、たとえ会社が合意退職に応じなかったとしても、申入れから2週間を経過することで自動的に退職(辞職)が成立するということです。
辞職をするにあたって、特別な理由は必要ありません。
解雇
解雇とは、会社側の意思表示によって従業員を辞めさせることです。
解雇は会社側の一方的な意思表示で成立するため、従業員の合意は必要ありません。
そうであるからこそ、解雇については労働契約法で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されるなど、厳しく制限されています(労働契約法16条)。
会社の一方的な都合によって簡単に解雇されてしまうと、従業員の立場が非常に不安定なものとなるためです。
そのため、解雇はしばしば「合理的な理由があったか、社会通念上相当であったか」などが問題視され、解雇無効を訴えたり損害賠償請求をされたりするトラブルへと発展します。
会社としては、このような事態を避けるため、可能な限り合意退職を試みます。
そのうえで、やむを得ず解雇する場合には、解雇が相当である証拠を積み重ねておくことが重要です。
解雇にまつわるトラブルは少なくありません。
解雇したい従業員がいる場合は、あらかじめ社労士や弁護士などの専門家へご相談ください。
退職の手続きの進め方

従業員の退職(合意退職)は、どのように進めればよいのでしょうか?
ここでは、退職手続きの進め方を解説します。
退職について話し合う
従業員から退職の申し出があったら、申し出と真摯に向き合い、まずは話し合いを試みます。
退職を思いとどまってほしいのであれば、会社がその従業員を必要としている旨を誠実に伝えましょう。
なお、先ほど解説したように、たとえ会社側が退職に応じなくても、退職の申し入れから2週間が経つと雇用契約は自動的に終了します。
そのため、たとえば「引継ぎが終わるまでは在職してほしい」「繁忙期が終わるまでは辞めないでほしい」などの希望があったとしても、あくまでもお願いでしかありません。
引継ぎが終わるまで在職することや繁忙期が終わるまで退職を待つことは従業員側の義務ではないため、誤解のないよう注意してください。
一方、会社側から退職を申し入れる退職勧奨をする際は、違法な退職強要とならないよう進め方に注意が必要です。
適法な退職勧奨はあくまでも会社側が退職を「勧める」だけであり、従業員側がこれに応じる義務はありません。
事実上退職に応じることが強制されていれば、解雇や違法な「退職強要」と判断され、トラブルとなるおそれがあります。
そのため、退職勧奨をする際はあらかじめ社労士などの専門家へ相談のうえ、慎重に進める必要があります。
退職に関する合意書を取り交わす
退職について合意が成立したら、会社と従業員とで退職に関する合意書を取り交わします。
退職合意書を交わしておくことで合意退職であることが明確となるうえ、退職の撤回を避けることが可能となります。
また、合意書の中に守秘義務条項などを盛り込むことで、在職時に知った機密情報が漏洩する事態を防ぎやすくなります。
ほかにも、「本合意書に定めるほか一切の債権債務のないことを相互に確認する」などの清算条項を設けることで、退職後に未払い残業代などを請求される事態を避けやすくなります。
このように、退職合意書は後のトラブル予防対策として非常に有用です。
そのため、退職の合意ができたら、必ず退職合意書を取り交わしておきましょう。
合意書に記載すべき内容がわからない場合は、社労士へご相談ください。
就業規則による退職の制限に強制力はある?
就業規則で、退職に関する制限規定を設けることがあります。
では、就業規則で退職を制限した場合、その定めに強制力はあるのでしょうか?
退職を禁じる規定
非常に有能な従業員である場合、会社は辞めてほしくないことでしょう。
そのため、定年まで退職できない旨や、退職するには必ず会社の許可が必要な旨を定めたいと考えるかもしれません。
しかし、このような規定は無効です。
なぜなら、日本国憲法の22条で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」と規定されており、退職の禁止はこの職業選択の自由に違反する可能性が高いためです。
退職する場合は3か月前までに申し出るべき旨の規定
会社としては、従業員に突然退職される事態は避けたいことでしょう。
そこで、引継ぎや人材の補充にかかる時間を確保するため、就業規則に「退職する場合は3か月前に通知すること」などと規定することが少なくありません。
このような定めを、就業規則に設けること自体は可能です。
しかし、先ほど紹介したとおり、民法では退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了すると定められています。
就業規則に3か月前までに退職を申し入れるべきことを定めても、民法の規定より長い期間は、会社からのお願いでしかありません。
つまり、従業員が自主的に就業規則に従って3か月前までに退職を申し入れることは問題がない一方で、民法どおり2週間後に退職したいと主張する従業員を無理に引き留めることはできないということです。
就業規則を盾に、退職の通知から3か月経たないと退職させないとしてその期間中の勤務を強要すると、損害賠償請求などの原因となる可能性があります。
退職に関する労使間のよくあるトラブル
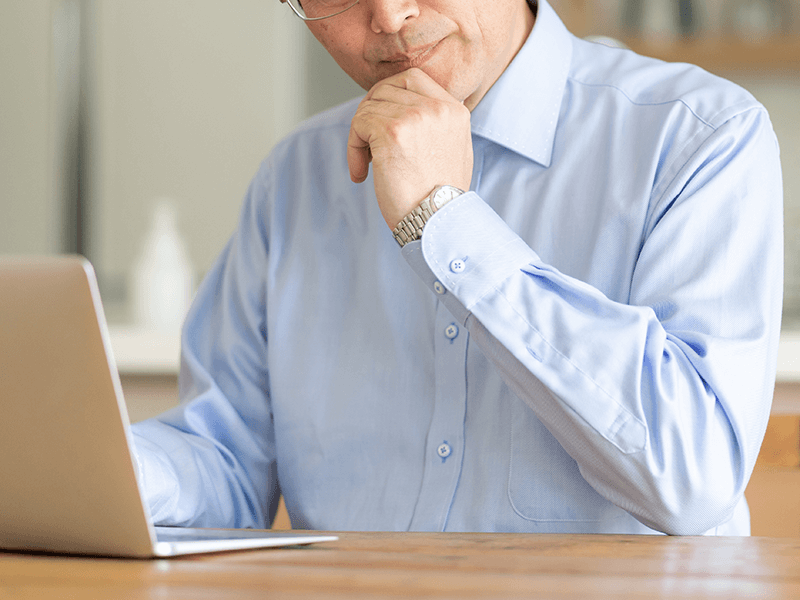
退職に関しては、労使トラブルに発展するケースが少なくありません。
最後に、退職に関する労使間のよくあるトラブルを3つ紹介します。
従業員はすぐに退職したい一方で、会社が退職を引き留めるトラブル
1つ目は、従業員はできるだけすぐに退職したいと希望する一方で、会社が退職を引き留めることによるトラブルです。
確かに、後任者が仕事を覚えるまでの間や、繁忙期を過ぎるまでの間、退職しないでほしいとの考えは十分に理解できます。
しかし、法律(民法)上では退職の申し入れから2週間後に雇用契約が終了するとされています。
そして、会社がこれを超えて在職期間を伸長するよう強制することはできません。
就業規則で退職の申し入れから退職までの期間をこれより長く設定することはできるものの、2週間を超える期間については、あくまでも会社からのお願いです。
2週間を超える期間の在職を強要すると、従業員側から損害賠償請求をされる可能性があります。
有給消化に関するトラブル
2つ目は、有給休暇の消化にまつわるトラブルです。
従業員は、残っている有給休暇を消化したうえで退職したいと考えることが多いでしょう。
一方、会社としては、少なくとも退職の申し入れから民法で規定された2週間は出勤してもらい、有給休暇を消化する場合はその後にしてほしいと考えることが少なくありません。
実は、法律上は従業員側の主張がとおります。
つまり、有給休暇が多く残っている場合、退職の通知した翌日からそのまま有給休暇に入り、通知後一度も出勤することなく退職日を迎える事態もあり得るということです。
また、会社は有給休暇の時期をずらしてもらう「時季変更権」があるものの、退職する従業員はその後有給休暇を使う機会がないことから、時季変更権は使えません。
そのため、出勤をしてほしい場合、出勤を強要するのではなく、あくまでもお願いするほかないでしょう。
有給休暇の取得を禁じたり出勤を強要したりすれば、トラブルに発展する可能性があります。
引き継ぎ期間に関するトラブル
3つ目は、引継ぎ期間に関するトラブルです。
従業員が退職する場合、会社としては、少なくとも十分な引き継ぎをしてほしいと考えるでしょう。
しかし、先ほど解説したように有給休暇を取得されてしまうと、退職通知の後出勤することなく退職してしまう事態が生じ得ます。
では、引継ぎをせずに退職した従業員に対いて、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか?
結論としては、「不可能ではないものの、難しい」といわざるを得ません。
まず、一切引継ぎをすることなく、会社側の「引継ぎをしてほしい」との申し入れも聞かず退職を強行したことによって会社に損害が生じた場合、従業員に対して損害賠償請求をすること自体は不可能ではありません。
しかし、損害賠償請求をするには、引継義務違反と損害の発生との間に因果関係があることを会社側が証明しなければならず、この証明は容易ではないでしょう。
そのため、まずは引継ぎをしてもらうよう従業員にお願いすることが必要です。
また、退職日の前2週間の間に引き継をしなった場合に退職金を不支給とする旨の定めを退職金規定に設けることも、検討の余地があります。※1
退職する従業員の引き継ぎ期間の確保についてお困りの際は、社労士へご相談ください。
まとめ
就業規則による退職の制限規定について解説しました。
就業規則で、退職を禁止したり許可制としたりすることはできません。
一方で、退職の通知から退職までの期間を、民法よりも長い期間とする定めは可能です。
ただし、民法に規定された2週間を超える期間については、あくまでも会社からのお願いとなります。
そのため、その期間の出勤を強要できないことには注意が必要です。
退職に関する就業規則の規定でお困りの際は、社労士にご相談ください。
Authense社会保険労務士法人では就業規則の作成支援に力を入れており、さまざまな規模、さまざまな業種の企業について就業規則のサポート実績があります。
退職にまつわる就業規則の規定でお悩みの際は、Authense社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。
参考文献
監修者

東京都社会保険労務士会所属。成蹊大学文学部英米文学科卒業。 創業間もないベンチャー企業だったAuthense法律事務所と弁護士ドットコムの管理部門の構築を牽引。その後、Authense社会保険労務士法人を設立し代表に就任。企業人事としての長年の経験と社会保険労務士としての知見を強みとする。
お悩み・課題に合わせて最適なプランをご案内致します。お気軽にお問合せください。






